企業研究インフラ編では、エネルギー部門の中から石油業界をピックアップしました。
石油業界は石油製品の精製販売が主体の元売りと、原油・天然ガスの開発生産の2つの分野に分かれています。
その両方を行っている会社もありますが、日本ではどちらかを主として行っていることが多いです。
今回の企業研究では、石油製品の精製販売の国内2トップの「ENEOSホールディングス」と「出光興産」、そして原油・天然ガスの開発生産量国内1位の「国際石油開発帝石」を比較して見ていきます。
1.インフラとは
 インフラとは、英語のinfrastructureを略した言葉で、“基盤”を意味します。
インフラとは、英語のinfrastructureを略した言葉で、“基盤”を意味します。
つまり「人が社会生活を送る上で不可欠な基盤」を指します。
インフラの例としては、道路、鉄道、上下水道、電気、IT、通信、インターネットなどが上げられます。
2.エネルギー業界について
 インフラの中でもエネルギー業界といえば、石油・電力・ガスの3つを指すことが多いです。
インフラの中でもエネルギー業界といえば、石油・電力・ガスの3つを指すことが多いです。
日常生活の中ではそれぞれガソリン・電気・ガスが私たちの身近で生活を支えてくれています。
電力とガスに関してはそれぞれ2000年と2017年から小売自由化が進み、「新電力」と呼ばれる企業が続々と参入しており価格競争も激化しています。
一方石油は今後低燃費のエコカーや電気自動車の普及に伴い、ガソリン需要は減少していくこととなります。
そこで経営合理化に向け会社を統合していく動きがありました。
ちなみに石油は1998年に精製業の需要調整規制が廃止され、2002年に自由化しており、規制緩和の検討が始まった1994年以降2000年にかけて価格競争が激化した時代がありました。
3.石油業界について
 石油事業は大きく分けて油田開発・原油採掘といった上流部門と、原油の精製・販売を行う下流部門に分かれます。
石油事業は大きく分けて油田開発・原油採掘といった上流部門と、原油の精製・販売を行う下流部門に分かれます。
利益が大きい上流部門は欧米の石油メジャー(国際石油資本:石油の採掘から販売の事業を手掛けている石油系巨大企業の総称)や中東諸国の力が強く、日本の石油会社は下流部門が中心です。
原油の99%以上は輸入に頼っており、原油価格の動きに業績が左右されるという面があります。
2017年にはJXホールディングスと東燃ゼネラル石油が経営統合し、JXTGホールディングスに(現ENEOSホールディングス)、2019年には出光興産が昭和シェル石油を完全子会社化しました。
国内の販売シェアとしてはENEOSホールディングスが47%、出光興産が31%、コスモ石油が14%を占めています(2018年度石油資料より)
業界再編により度を超えた価格競争は姿を消し、各社の経営は数年前に比べて大幅に改善しました。
しかし現在は新型コロナウイルスによるジェット機を始めとする燃料油の需要が落ちたことによって各社苦戦を強いられています。
ENEOSホールディングスはガソリンスタンドのENEOSを展開し、石油販売だけでなく銅などの非鉄金属の開発や海外での石油・天然ガスの開発、東京電力と大阪ガスと提携し電力とガスの小売りも行っています。
出光興産は石油化学に強く、北海で原油・ガスの開発生産、豪州で石炭開発、アジアでの石油精製販売に加え、有機EL材料(スマートフォンやテレビなどのディスプレイに使われている)など成長分野へも参入しています。
今後の課題としては需要が減っていく石油販売事業の合理化、化学品原料としての用途開発や、家庭向けの都市ガス事業への参入などガソリン以外の事業での収益アップが鍵となります。
一方原油・天然ガスの開発生産を行っている国際石油開発帝石は、石油・ガス開発の国内専業最大手です。
「国際石油開発」と「帝国石油」が統合してできた会社で、日本政府(経済産業大臣)が筆頭株主となっています。
オーストラリアでの大型ガス開発・液化天然ガス事業を推進しています。
今後、インドネシアでの開発案件も予定しており、ガス生産で存在感を増しています。
4.企業研究のポイント
 企業研究をすることで目指すのは、その会社の仕事をしっかりと理解して自己PRや面接での受け答えにつなげることにあります。
企業研究をすることで目指すのは、その会社の仕事をしっかりと理解して自己PRや面接での受け答えにつなげることにあります。
多くの就活生は会社案内のパンフレットや就活サイトなどを読んで企業研究をしますが、企業全体のイメージを掴むことは難しいと思います。
企業研究で見るべきポイントは以下の通りです。
①会社の歴史
会社の成り立ちや手掛けてきた事業を知りましょう。

②主要な数字と株主構成
売上高や従業員数、株主構成を見て企業を比較しましょう。
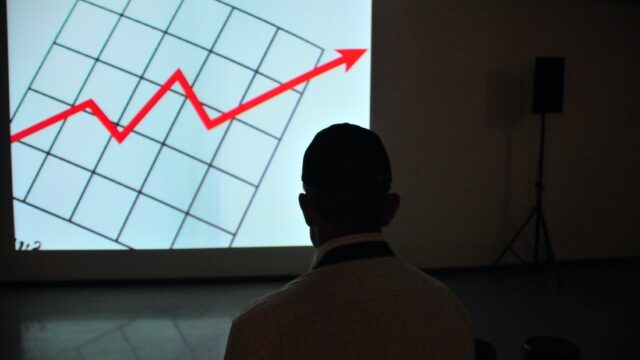
③ビジネスモデル
現在どのようなビジネスを展開しているのか知りましょう。

④決算書
どの商品や事業が会社を支えているのか、今後成長が見込める事業が何か知りましょう。

⑤企業理念と経営戦略
企業が大切にしている「想い」を知りましょう。

5.ENEOSホールディングス・出光興産・国際石油開発帝石 3社の企業研究
 それでは、具体的に企業研究を行っていきます。
それでは、具体的に企業研究を行っていきます。
企業のホームページや有価証券報告書を主に資料としています。
有価証券報告書は企業のホームページから見ることができます。
全ての語句やデータを知る必要はありません。
ポイントを押さえて見ていきましょう。
その他『会社四季報 業界地図』や図書館で希望の業界の本を何冊か読んでみるのもおすすめです。
『業界地図』では、どの会社がどの分野で国内何位なのかや、それぞれの業界のチェックすべきポイントを簡潔に知ることができます。![]()
①各社の歴史比較
ENEOSホールディングス
ENEOSホールディングスの歴史は戦前の1880年代後半にさかのぼります。
1888年に「有限責任日本石油会社」を創立したのが始まりです。
いくつかの石油会社が台頭し、日中戦争や太平洋戦争を経て高度経済成長を迎え企業の数が増えますが、バブル崩壊後に合併の動きが進みます。
東燃ゼネラル系のグループとJX系のグループに分かれますが、JX系では2008年に「新日本石油株式会社」(当時国内石油卸1位)と「新日鉱ホールディングス」(非鉄金属メーカーから石油事業に進出、当時国内石油卸6位)が経営統合し、2010年に「JXホールディングス株式会社」を設立することとなりました。
2017年には東燃系の「東燃ゼネラル石油株式会社」と合併し「JXTGホールディングス」に商号を変更、2020年6月にさらに「ENEOSホールディングス」に商号変更を行っています。
ちなみにJXTGには「J」ジャパン、「X」未知、「T」東燃、「G」ゼネラル石油、という意味が込められています。
また、ENEOSの由来は「ENERGY」“エネルギー”と「NEOS」ギリシャ語で“新しい”を掛け合わせた造語となっています。
出光興産
出光興産の前身は1911年に北九州の貿易港・門司で石油販売業を商う「出光商会」で、創業者は出光佐三(さぞう)です。
まずは機械用の潤滑油の販売から始まりました。
その後漁船燃料油の販売や南満州鉄道との取引を進め販路拡張と海外展開を行っていきます。
その後1943年には出光興産本社を東京へ移転します。
海外を中心に事業を展開していた出光は、1945年の敗戦によりほぼ全ての事業と在外資産を失いますが、異業種での事業でなんとか持ちこたえ1947年には石油業に復帰しました。
出光興産は国際石油資本の傘下に入らずに石油を手に入れるという独自路線の経営を続けます。
1957年に徳山製油所、1963年には千葉製油所(京葉工業地帯内)が完成し、千葉製油所は現在も出光の基幹製油所となっています。
2006年に東京証券取引所第一部に上場。2019年4月には「昭和シェル石油」と経営統合した際は出光創業家の反対がありましたが後に賛成に転じ、出光正和が出光興産の取締役(非常勤)になっています。
国際石油開発帝石
国際石油開発帝石は、「国際石油開発株式会社」と「帝国石油株式会社」(帝石)の合併により今のネーミングとなっています。
帝国石油は1941年に半官半民の国策会社として設立し、1950年には民間会社として再発足されました。
1960年に南関東ガス田で水溶性ガス開発開始、1962年に新潟~東京間に国内初の長距離高圧天然ガス輸送パイプライン(海上での輸送はタンカーですが、陸上ではパイプが使われています)を完成させます。
また、1960年代からは海外での採鉱にも進出しています。
一方国際石油開発は1966年に「北スマトラ海洋石油資源開発株式会社」として設立されます。
インドネシア国営石油ガス会社と契約し、海外での石油資源の自主開発を始めます。
1973年にはアラブ首長国連邦のADMA鉱区の権益を取得、1975年に社名を「インドネシア石油株式会社」に変更しています。
その後帝国石油は新潟県でガス田を発見、国際石油開発はオーストラリア、中東、中央アジア・コーカサス、アフリカ、南米へも事業地域を拡大させています。
国際石油開発は特に2000年代にオペレーター(開発プロジェクトに参加する企業群の中心となる存在)としてイクシス(オーストラリアのガス田の名前)、アバディ(インドネシアのガス田の名前)の巨大ガス田を相次いで発見しました。
2006年に両社の共同持株会社「国際石油開発帝石ホールディングス株式会社」を設立し、2008年に合併しています。
〈比較結果〉
ENEOSは吸収合併を繰り返してきた歴史を持ち、国内シェアの5割を占めるまでになっています。
出光興産は創業者の出光佐三による功績が大きく、石油業界内でも唯一独自路線で大型合併をこれまで行わずにいましたが2019年に昭和シェル石油と経営統合しました。
ガソリンスタンドもENEOSはENEOSで統一、出光興産と経営統合した貝のマークの昭和シェル石油もIDEMITSUで統一されることになりました。
国際石油開発帝石は海外での石油開発と国内外での開発を行う2社の合併により誕生しました。
イクシスとアバディの開発・生産をオペレーターとして実現させていくこと、天然ガスを生産から販売まで管理運営していくことなどで将来を見据えています。
②主要な数字と株主構成
| ENEOSHD(2020年3月期) | 出光興産(2020年3月期) | 国際石油開発帝石(2019年12月期) | |
| 売上高(百万円) | 10,011,774 | 6,045,850 | 1,000,005 |
| 営業利益(百万円) | △113,061 | △3,860 | 498,641 |
| 営業利益率 | △1.1% | △0.06% | 49.9% |
| 当期純利益(百万円) | △172,735 | △22,935 | 123,550 |
| 準資産額(百万円) | 2,707,908 | 1,200,564 | 3,297,176 |
| 総資産額(百万円) | 8,011,292 | 3,886,938 | 4,849,995 |
| 自己資本比率 | 33.8% | 29.6% | 62.7% |
| 従業員数 | 40,983 | 13,766 | 3,117 |
| グループ会社の数 | 子会社 517社 持分法適用会社等 172社 | 連結子会社 170社 持分法適用会社 74社 | 連結子会社 65社 持分法適用会社 20社 |
☛用語解説
・営業利益
売上高から売上原価と人件費やビルの賃貸料、広告宣伝費などを差し引いた金額。
・当期純利益
税金の金額を差し引いた最終的な儲けの金額。
・準資産額
企業が所有している土地や建物などの「資産」から銀行からの借入金などの「負債」を差し引いた金額。
・自己資産比率
会社が調達した資金の中で返済を必要としない自己資金の割合。比率が高いほど企業経営が安定している。
〈比較結果〉
石油業界の2020年3月期は原油価格暴落による在庫評価損を受けて赤字となりました。以下のような仕組みです。
・原油価格が上昇すれば在庫分は仕入れ価格より原価が下がる→利益が上がる
・原価価格が下落すれば仕入れ価格より原価が上がる→利益が下がる
国際石油開発帝石は決算月が12月に変更されたことからまだ影響を受けていない数字になっています。
2020年4月からも新型コロナウイルスの影響により製油所の稼働率が下がり、業績に影響が出ています。
自己資本比率は国際石油開発帝石が62.7%とずば抜けて高い数字ですので、財務健全性は非常に高いと言えるでしょう。
グループ会社の数はENEOSホールディングスが多く、JXTGエネルギー、鹿島石油㈱(石油製品及び石油化学赤貧の製造メインの会社)、JX石油開発、JX金属㈱、㈱NIPPO(道路・舗装・土木工事、石油関連設備の企画・設計・建設)などがあります。
国際石油開発帝石は海外における探鉱・開発・生産の連結子会社の数が多く、出光興産には出光タンカー㈱、昭和四日市石油㈱(石油精製の会社)、東亜石油㈱(石油精製、発電を行っている)、エスアイエナジー㈱、リーフエナジー㈱、アポロリテイリング(SS関連商品の販売会社)などがあります。
株主構成
| ENEOSHD(2020年3月時点) | 出光興産(2020年3月時点) | 国際石油開発帝石(2019年12月時点) | |||
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.59% | 日章興産株式会社 | 9.11% | 経済産業大臣 | 18.96% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6.29% | Aramco Overseas Company B.V.(常任代理人 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) | 7.76% | 石油資源開発株式会社 | 7.32% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2.57% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.34% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.81% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 2.28% | 公益財団法人出光文化福祉財団 | 4.16% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4.01% |
| 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.21% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4.15% | ENEOSホールディングス株式会社 | 3.00% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.90% | 公益財団法人出光美術館 | 2.69% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2.20% |
| SMBC日興証券株式会社 | 1.84% | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.80% | 三井石油開発株式会社 | 1.85% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.63% | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.73% | ジェーピー モルガン チェース バンク 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.67% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.50% | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.73% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1.53% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.24% | 株式会社三井住友銀行 | 1.73% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.51% |
| 小計 | 29.05% | 小計 | 42.2% | 小計 | 47.86% |
| その他 | 70.95% | その他 | 57.8% | その他 | 52.14% |
| 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% |
〈比較結果〉
ENEOSの大株主は信託銀行や銀行が占めていて、安定した優良企業であることが分かります。
「日本トラスティ・サービス信託銀行」「日本マスタートラスト信託銀行」という聞きなれない名前が多いですが、これらは年金・投資信託などの運用を委託されている銀行です。
実際の株の買い手が分かりませんが、GPIFや日銀が買っている可能性が高く、信頼度の高い会社ということが分かります。
また、3株主は海外の機関投資家であり、外国人投資家の期待も高いと言えます。(外国人所有比率は34.1%です。)
出光興産は創業家によるオーナー企業の色合いが強いことが株主構成からも分かります。
大株主の第1位は創業家の資産管理会社である日章興産が9.11%、また公益財団法人出光文化福祉財団が4.16%、公益財団法人出光美術館2.69%となっています(計15.96%)
それぞれ出光佐三の長男がトップを務めています。
しかし、昭和シェル石油との合併前よりは創業家の持ち株比率は目減りしています。
国際石油開発帝石は経済産業大臣が18.96%を所有しており、経営に対して政府が介入できるということになっています。
第2位の石油資源開発株式会社とは互いに株式を持ち合い石油・天然ガス開発事業において協力関係にあります。
第5位のENEOSホールディングスは国際石油開発帝石の主要顧客であり、石油・天然ガス開発事業に関しても協力関係にあります。![]()
③ビジネスモデルを分析しよう
ENEOSホールディングス
(2020年3月)
| セグメント | 従業員数 | 構成比 |
| エネルギー | 22,407 | 54.7% |
| 石油・天然ガス開発 | 715 | 1.7% |
| 金属 | 9,747 | 23.8% |
| その他 | 8,114 | 19.8% |
| 合計 | 40,983 | 100% |
ENEOSホールディングスの事業は、4つに分かれています。
・エネルギー(石油精製販売、潤滑油、基礎化学品、機能化学品、ガス、石炭、電気、新エネルギー)
 国内で燃料油需要の減少が続いています。
国内で燃料油需要の減少が続いています。
海外では潤滑油や石油化学製品などの需要が長中期的に増加することを見込んでいます。
生産面では室蘭製造所の生産を停止し物流拠点化する、大阪製油所は精製機能を停止しアスファルト発電の事業所として再構築を決定するなどによって効率化を図っています。
販売面ではサービスステーションをENEOSへ統一を完了し、新しい決済ツール「EneKey」の導入や、コインランドリー併設やデリバリー型カーシェアリングサービスの実証試験を開始しました。
電気事業では「ENEOSでんき」の供給地域を関西・中部・東北・四国エリアに拡大し、2020年4月からは北陸・九州エリアで発売を開始しています。
また、米国オハイオ州にてグループ初となる海外天然ガス火力発電事業に参画しました。
ガス事業は関東圏で「ENEOS都市ガス」の拡販を図っています。
水素事業では全国41か所で「ENEOS水素ステーション」を運営し、再生可能エネルギー事業では台湾最大級の洋上風力発電事業に参画、加えて室蘭市においてバイオマス発電所の建設を進めています。
潤滑油事業は海外展開を進め、機能材事業では健康食品向けカロテノイド(動植物に存在する黄色または赤色の色素。強い抗酸化作用を持つ)事業分野でインドの企業と協業を始めました。
・石油・天然ガス開発(石油・天然ガスの探鉱・開発及び生産)
 北海(イギリス)、UAE・カタール、ミャンマー、ベトナム、マレーシア、インドネシア、パプアニューギニア、日本、アメリカ・メキシコ湾で石油・天然ガスの開発を行っています。
北海(イギリス)、UAE・カタール、ミャンマー、ベトナム、マレーシア、インドネシア、パプアニューギニア、日本、アメリカ・メキシコ湾で石油・天然ガスの開発を行っています。
・金属(非鉄金属資源の開発・採掘、銅、金、銀、硫酸、銅箔、圧延・加工材料、薄膜材料、非鉄金属リサイクル・産業廃棄物処理、非鉄金属製品等の船舶運送、チタン、電線)
 先端素材の製造・開発、さらに使用済み電子機器からのリサイクルまで、銅・レアメタルを中心とした非鉄金属に関する事業をグローバルに展開しています。
先端素材の製造・開発、さらに使用済み電子機器からのリサイクルまで、銅・レアメタルを中心とした非鉄金属に関する事業をグローバルに展開しています。
日本の他にアジア、欧州、中東、北米、南米に拠点を持っています。
・その他(アスファルト舗装、土木工事、建築工事、陸上運送、不動産賃貸、資金調達等のグループ共通業務)

出光興産
(2020年3月31日現在)
| 事業区分 | 従業員数 | 構成比 |
| 燃料油 | 6,686 | 48.6% |
| 基礎化学品 | 788 | 5.7% |
| 高機能材 | 3,307 | 24.0% |
| 電力・再生可能エネルギー | 813 | 5.9% |
| 資源 | 1,212 | 8.8% |
| その他・調整 | 960 | 7.0% |
| 合計 | 13,766 | 100% |
出光興産の事業は6つに分類されます。
・燃料油
 原油・石油製品の輸送、石油の精製、石油関連製品の製造、石油製品・SS関連商品の販売、LPGの輸入・仕入及び販売、石油関連設備等の設計・建設、海外における原油等の売買・石油製品の製造及び販売、クレジットカード事業が含まれます。
原油・石油製品の輸送、石油の精製、石油関連製品の製造、石油製品・SS関連商品の販売、LPGの輸入・仕入及び販売、石油関連設備等の設計・建設、海外における原油等の売買・石油製品の製造及び販売、クレジットカード事業が含まれます。
海外事業ではベトナムの製油所を2018年よりスタートしており、シンガポールの現地法人の出光アジアを中心に海外拠点の事業拡充を進めています。
・基礎化学品
 石油化学原料・製品の製造及び販売を行っています。
石油化学原料・製品の製造及び販売を行っています。
石油精製によって得られる原料でOA、電気、電子、自動車向け製品やプラスチック加工品を製造しています。
・高機能材
 潤滑油の製造及び販売、石油化学原料・製品の製造及び販売、電子材料の製造・販売・ライセンス事業、建築・土木・道路用合材の製造及び販売、農薬等の製造・輸入及び販売が含まれます。
潤滑油の製造及び販売、石油化学原料・製品の製造及び販売、電子材料の製造・販売・ライセンス事業、建築・土木・道路用合材の製造及び販売、農薬等の製造・輸入及び販売が含まれます。
自動車用潤滑油の分野では販売台数が伸びているアジア等の新興国での拡充を図っています。
また、EV向けの潤滑油やグリースの開発に取り組んでいます。
出光は国内唯一の総合アスファルトメーカーとして国内外で事業を行っています。
・電力・再生可能エネルギー
 太陽電池の製造及び販売、電力の共有・販売を行っています。
太陽電池の製造及び販売、電力の共有・販売を行っています。
再生可能エネルギーは風力、太陽光、バイオマス、地熱発電といったエネルギー電源を有しています。
海外では北米でガス火力発電事業、北米と東南アジアで再生可能エネルギー事業を行っています。
・資源
 石油資源・地熱資源の調査、探鉱、開発及び販売、石炭・ウランの調査、探鉱、開発及び販売を行っています。
石油資源・地熱資源の調査、探鉱、開発及び販売、石炭・ウランの調査、探鉱、開発及び販売を行っています。
ノルウェー・東南アジアを中心に石油・ガスの探鉱・開発を、オーストラリア・インドネシアにて石炭鉱山事業を、カナダ・シガーレイク鉱山でウラン鉱石を生産しています。
・その他
その他の事業として、ガスの輸入、仕入及び販売、海外サービス機能会社、保険代理店事業を行っています。
国際石油開発帝石
(2019年12月時点)
| セグメント | 従業員数 |
| 日本 | 953 |
| アジア・オセアニア | |
| ユーラシア(欧州・NIS諸国) | |
| 中東・アフリカ | |
| 米州 | |
| 全社(共通) | 256 |
| 合計 | 1,209 |
国際石油開発帝石は地域ごとにセグメントが分かれていますが、それぞれの地域の従業員数を知ることができませんでした。事業としては以下の3つの取り組みを進めています。
①石油・天然ガス上流事業の持続的成長
②グローバルガスバリューチェーンの構築(2040年に向けて日本のみならずアジア・オセアニアを中心とした地域で天然ガス開発・供給の主要プレーヤーとなることを目指す)。
③再生可能エネルギーの取り組みの強化
1)生産実績
| セグメント | 区分 | 2019年12月期 | 生産量順位 |
| 日本 | 原油 | 0.9百万バレル | 原油生産5位 |
| 天然ガス | 32.6十億CF | 天然ガス生産2位 | |
| ヨード | 376.1t | ||
| 発電 | 151.7百万kWh | 発電生産2位 | |
| アジア・オセアニア | 原油 | 13.1百万バレル | 原油生産2位 |
| 天然ガス | 280.4十億CF | 天然ガス生産1位 | |
| 発電 | 286.9百万kWh | 発電生産1位 | |
| ユーラシア(欧州・NIS諸国) | 原油 | 13.1百万バレル | 原油生産2位 |
| 天然ガス | 6.7十億CF | 天然ガス生産4位 | |
| 硫黄 | 64.8千t | ||
| 中東・アフリカ | 原油 | 67.3百万バレル | 原油生産1位 |
| 米州 | 原油 | 2.5百万バレル | 原油生産4位 |
| 天然ガス | 17.5十億CF | 天然ガス生産3位 | |
| 合計 | 原油 | 96.9百万バレル | |
| 天然ガス | 337.3十億CF | ||
| ヨード | 376.1t | ||
| 発電 | 438.6百万kWh | ||
| 硫黄 | 64.8千t |
2)販売実績
| セグメント | 区分 | 販売量 | 売上高(百万円) | 販売額順位 |
| 日本 | 原油 | 499千バレル | 3,647 | 原油販売5位 |
| 天然ガス(LPGを除く) | 56,242百万CF | 80,282 | 天然ガス販売2位 | |
| LPG | 3千バレル | 16 | LPG販売2位 | |
| その他 | 13,092 | |||
| 小計 | 97,038 | |||
| アジア・オセアニア | 原油 | 14,008千バレル | 101,577 | 原油販売2位 |
| 天然ガス(LPGを除く) | 262,903百万CF | 136,237 | 天然ガス販売1位 | |
| LPG | 409千バレル | 3,112 | LPG販売1位 | |
| 小計 | 240,927 | |||
| ユーラシア | 原油 | 11,272千バレル | 77,867 | 原油販売3位 |
| 天然ガス(LPGを除く) | 6,720百万CF | 1,412 | 天然ガス販売4位 | |
| その他 | △225 | |||
| 小計 | 79,054 | |||
| 中東・アフリカ | 原油 | 79,147千バレル | 569,166 | 原油販売1位 |
| 米州 | 原油 | 2,024千バレル | 11,781 | 原油販売4位 |
| 天然ガス(LPGを除く) | 19,317百万CF | 2,038 | 天然ガス販売3位 | |
| 小計 | 13,819 | |||
| 合計 | 原油 | 106,950千バレル | 764,039 | |
| 天然ガス(LPGを除く) | 345,182百万CF | 219,970 | ||
| LPG | 412千バレル | 3,128 | ||
| その他 | 12,867 | |||
| 合計 | 1,000,005 | |||
〈比較結果〉
ENEOSホールディングスと出光興産は、石油の精製販売や基礎化学品といった事業に大多数の人員が配置されています。
石油を原料とした各種製品の生産や電力や水素、再生可能エネルギーの供給にも力を入れています。
国際石油開発帝石は主にアジア・オセアニアと中東・アフリカが生産・販売ともに多くを占めています。
それぞれの地域の従業員数を知ることはできませんが、グローバルに活躍できる人材が求められています。
④決算書から会社の現在と未来を知ろう
ENEOSホールディングス(2020年3月期決算短信より)
※売上高と営業利益の上位3位に赤い色付けを行っています。
(単位:百万円)
| ENEOSホールディングス | 売上高 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 |
| エネルギー | 8,419,444 | 83.7% | △162,766 | △140.5% |
| 石油・天然ガス開発 | 133,364 | 1.3% | △38,801 | △33.5% |
| 金属 | 1,004,413 | 10.0% | 44,631 | 38.5% |
| その他 | 507,352 | 5.0% | 41,076 | 35.5% |
| 計 | 10,064,573 | 100.0% | △115,860 | △100.0% |
| 調整額 | △52,799 | 2,799 | ||
| 合計 | 10,011,774 | △113,061 |
出光興産(2020年3月期決算短信より)
(単位:億円)
| 出光興産 | 売上高 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 |
| 燃料油 | 48,210 | 79.7% | △1,094 | 399.3% |
| 基礎化学品 | 4,592 | 7.6% | 119 | △43.4% |
| 高機能材 | 3,938 | 6.5% | 284 | △103.6% |
| 電力・再生可能エネルギー | 1,277 | 2.1% | △5 | 1.8% |
| 資源 | 2,418 | 4.0% | 418 | △152.6% |
| その他・調整額 | 23 | 0.1% | 4 | △1.5% |
| 計 | 60,459 | 100.0% | △274 | 100.0% |
| 調整額 | ― | 11 | ||
| 合計 | 10,439 | △262 |
国際石油開発帝石(2019年12月期 有価証券報告書より)
(単位:百万円)
| セグメント | 売上高 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 |
| 日本 | 97,038 | 9.7% | 13,156 | 2.6% |
| アジア・オセアニア | 240,927 | 24.1% | 117,801 | 23.1% |
| ユーラシア(欧州・NIS諸国) | 79,054 | 7.9% | 20,806 | 4.1% |
| 中東・アフリカ | 569,166 | 56.9% | 364,467 | 71.5% |
| 米州 | 13,819 | 1.4% | △6,545 | △1.3% |
| 計 | 1,000,005 | 100.0% | 509,685 | 100.0% |
| 調整額 | ― | △11,044 | ||
| 合計 | 1,000,005 | 498,641 |
〈比較結果〉
ENEOSホールディングスは期末にかけて原油価格が大幅に下落し、在庫評価による損失を計上したことと、中国で石油化学製品の大型新設設備の稼働を開始したが新型コロナウイルスや暖冬の影響で供給過剰となったことで「エネルギー事業」の損失が、さらに「石油・天然ガス開発事業」では減損損失の計上が原因で売上高が減少し、両事業で大きな損失が出ています。2021年3月期では営業利益1100億円を見込んでいます。
出光興産もENEOSと同じく原油価格の急落そして持分法投資損失の増加により燃料油セグメントが赤字になっています。
国際石油帝石は原油・天然ガスの探鉱、開発、生産事業で確認埋蔵量の9割超は海外ですので、業績は原油及び天然ガスの価格と為替レートの変動で大きく左右されます。
2019年度より3月ではなく12月が決算月となった関係でまだ原油価格の下落の影響を受けていない数字になっていますが、2020年12月期では利益縮小が予想されています。
次に、ENEOSHDと出光興産、両社の海外売上高を比較してみましょう。
ENEOSホールディングスと日本製紙の海外売上高
(単位:百万円)
| ENEOSHD | 日本 | 中国 | 他アジア | その他 | 計 |
| 売上高 | 7,911,283 | 571,716 | 788,143 | 740,632 | 10,011,774 |
| 割合 | 79.0% | 5.7% | 7.9% | 7.4% | 100.0% |
(単位:百万円)
| 出光興産 | 日本 | アジア・オセアニア | 北米 | 欧州 | その他地域 | 合計 |
| 売上高 | 4,740,127 | 844,313 | 341,067 | 89,182 | 31,159 | 6,045,850 |
| 割合 | 78.4% | 14% | 5.6% | 1.5% | 0.5% | 100.0% |
両社共に日本での売上が8割弱を占めています。
出光興産はアジア・オセアニアでの売上が14%とENEOSよりやや高い数字が出ています。
出光は50年近くに渡って潤滑油を通して海外進出しており、その影響が現れていると推測できます。中国では2か所目となる潤滑油工場が生産開始しています。
⑤企業理念と経営戦略
それぞれ確認しましょう。
■ENEOSホールディングス
・ENEOSグループ理念
https://www.eneos.co.jp/company/about/philosophy.html
・ENEOS 経営戦略
https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/strategy.html
■出光興産
・経営ビジョン
https://www.idss.co.jp/company/policy/index.html
・中期経営計画(2020~2022年度)
https://www.idss.co.jp/news/2019/191114_7.pdf
■国際石油開発帝石
・経営理念・企業行動憲章
https://www.inpex.co.jp/company/philosophy.html
・ビジョン2040
https://www.inpex.co.jp/company/vision.html
6.【番外編1】石油業界と外資系の関係
石油業界は以前、外資系の会社が存在していた時期があります。外資系ではない企業を民族系と呼んでいました。
民族系は、以前の名前なら日本石油(現ENEOS、1996年まではメジャーズのカルテックス現シェブロンと業務提携)、出光興産、ジャパンエナジー(現ENEOS)やコスモ石油です。
外資系は、国際石油開発資本(メジャーズ)などと資本関係があるエッソやモービル(エクソンモービル→東燃ゼネラル→現ENEOS)、昭和シェル石油(現出光興産)などです。
ただし米エクソンモービルは、東燃ゼネラルに持ち株を売却して、資本としては日本を撤退しました。
またロイヤル・ダッチ・シェルも、昭和シェルの持ち株を出光興産に売却しています。
その一方、中東産油国の資本参入も始まりました。
コスモ石油の筆頭株主はアラブ主張国連邦(UAE)系の投資会社で20.7%の株を持っています。
2002年1月に石油業法が廃止されるまで、精製設備の新設と増設は許可制でした。
外資系石油会社より民族系石油会社が優先されていましたが、石油業法廃止以降は原則自由となり民族系、外資系の垣根を越えた合併の動きにも繋がりました。
7.【番外編2】石油開発の歴史
19世紀:アメリカ中心の時代。
1859年アメリカペンシルバニア州で石油を掘り当てたことが始まりです。
20世紀:中東油田の発見クウェート、サウジアラビアに続き、ベネズエラ、中国、ロシアでも発見。
20世紀後半:イギリスで北海油田を発見。
石油の開発そして利用はこの150年強の間に行われてきた比較的新しい分野です。
8.まとめ
石油大手は初任給も高く平均年収もおおよそ800万~900万円台です。
石油業界は企業ごとに成り立ちが異なっていますし、合併が進んでいるため働いている人がたどってきた会社も様々です。そういったことを理解した上で就職活動に臨むことが大切です。
出光興産に関しては、創業者をモデルにした百田尚樹の小説『海賊とよばれた男』が有名ですので、読んでおくと良いでしょう。業界と企業のことを知ったら、どのような職種があるか一通り調べ、自分はどの分野で力を発揮できるかを考えてみましょう。
また、最近身近なトピックスとしてビニール袋の削減が進んでいます。界面活性剤や農薬の問題も少しずつ聞くようになりました。そのようなことについて自分なりに調べて、作る側の立場や消費者の立場になって考えを整理しておくことも必要です。










